「断捨離をしたいけど、何から手をつければいいのかわからない」
「捨てようと思っても、どれも必要な気がして手が止まってしまう」
そんなふうに感じている人は、多いのではないでしょうか。
実は、断捨離がうまくいくかどうかは「順番」で決まります。
捨てる順番を間違えると、モノへの執着や判断疲れに押しつぶされて、途中で挫折します。
でも、逆に“正しい順番”で進めれば、スムーズに、そして気持ちよく片づけが進んでいきます。
今日は、持ち物211個、服27着で暮らす僕自身が実践し、「これは間違いない」と確信している“断捨離の順番”を紹介します。
結論から言えば、最初に手をつけるべきは 「明らかなゴミ」 で、ステップ別に分けると
です。
理由などあわせて、ステップを追って解説していきます。
※本記事は、日本のミニマリストの先駆け、四角大輔さんの「超ミニマル主義」をベースに、私の経験も踏まえて作成したものです。
気になる方は、四角さんの本も読んでみてください!
目次
1.明らかなゴミ|まずは勢いをつける

最初の一歩として最もおすすめなのが、「どう考えても捨てていいもの」から始めること。
たとえば:
• 空になった洗剤のボトル
• 破れたビニール傘
• 明らかに使っていない空き箱や包装紙
• 賞味期限が切れた食品
こういった「判断力ゼロで捨てられるもの」は、迷うことなく手放せます。
断捨離は「勢い」が命。
最初に成功体験を積んでおくことで、次のステップに進む自信がつくのです。
2.洗面所・風呂場・洗濯機周り・掃除用具|感情が絡みにくい場所を選ぶ

次におすすめなのが、水回りです。
ここには、機能で判断できるモノが多くあります。
• 使っていないシャンプーや化粧品
• 毛先が広がった歯ブラシ
• 使い切れていない洗剤のストック
「まだ使えるかどうか」「清潔かどうか」といったシンプルな基準で、迷いなく判断できます。
水回りは感情が入りにくいエリアなので、「捨てる感覚」を養うにはぴったりです。
3.キッチン周り|使用頻度と賞味期限で判断

ここは食器、調理道具、食品などが中心で、判断ポイントは「いつ使ったか?」と「賞味期限」です。
•同じようなフライパンが3つある
•来客用に買ったけど結局使っていないマグカップ
•何年も奥に眠っていた調味料
こうしたものは、「今の自分にとって必要か?」という視点で客観的に選別できます。
キッチンは毎日使う場所なので、スッキリさせると日々の生活がぐっとラクになりますよ。
4.雑貨・小物|“なんとなく持ってる”を手放す

ここからは少し難易度が上がります。
文房具、ポーチ、インテリア雑貨、ノベルティグッズなど、「なんとなく持っているもの」が増えやすいのが雑貨です。
「これ、何に使うんだっけ?」
「いつか使うかもと思って取っておいたけど…」
というモノたちと、向き合うトレーニングの場だと思ってください。
手放す際は、判断の軸を明確に持つことが重要です。
たとえば、
•1年間使わなかったら手放す
•代用品があるものは減らす
•「なくても困らな」なら手放してOK
そんな基準で進めていきましょう。
5.趣味のもの|いまの自分に必要か?

本、楽器、カメラ、ゲーム、手芸道具など、「自分の好きなこと」に関わるモノは、判断が難しいぶん、捨てられると大きなスッキリ感があります。
ここでの問いは、
「これは、いまの自分に本当に必要か?」
過去の趣味、過去の目標、過去の憧れ。
それらを抱えたままでは、未来を身軽に生きていけません。
「またいつかやるかも」という未来への期待よりも、
「今、心が動くか?」を大事にしてみてください。
私も、3年前まで野球をやってたのですが、現在はやってないので野球道具をいくつか手放しました。
それでも今の生活には十分で、また大切な思い出が消える、なんてこともありません。
6.紙類|“情報”を手放して、頭も空間もスッキリ
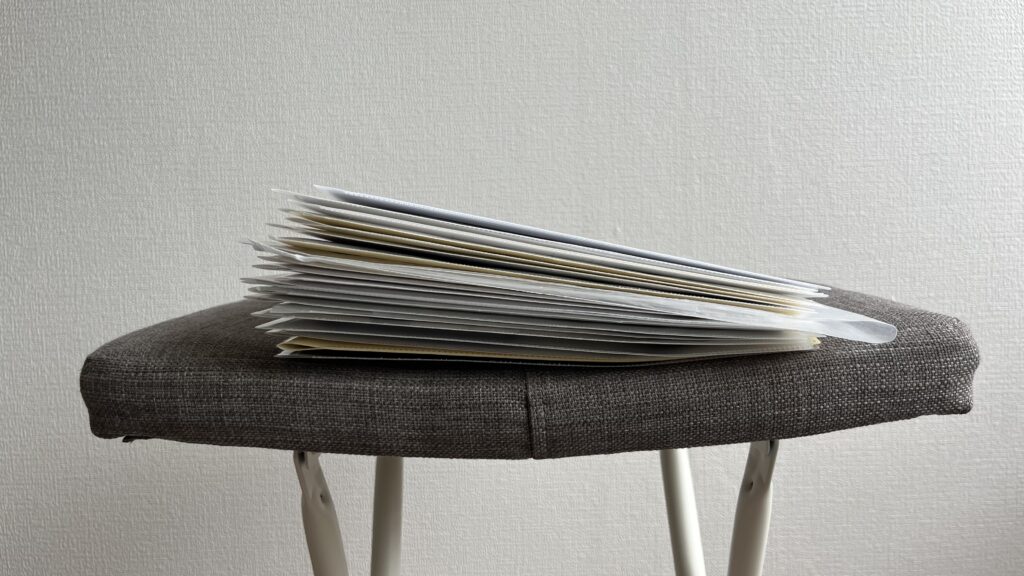
取扱説明書、DM、古いノート、使っていないプリント類など。
紙類はスペースを取らない分、「とりあえず保管」で溜まりがちです。
でも実は、紙を減らすことで、頭の中のノイズが一気に減ります。
今では、説明書はネットで見られるし、重要書類以外は写真で残すだけでも充分。
「本当に紙で残す必要があるか?」と自問してみましょう。
私も、全ての書類を写真で撮ってiCloudに保存しているので、実際手元にある総量は厚さ7㎝程度。
出先で書類の情報が必要になっても、スマホで探せるのですごく便利ですよ。
※書類以外にも、本の断捨離方法を知りたい方はこちら。
7.衣類・靴|感情も未来も背負っている

洋服は、見た目・思い出・未来の自分、すべてと関わっている難所です。
「高かったから」
「痩せたら着るつもり」
「これを着ていた頃は…」
そんな理由で捨てられない服が多いのは当然です。
でも、今のあなたに似合わない服は、いくらあっても人生を豊かにはしてくれません。
基準はシンプル。
•今、着ているか?
•鏡を見て気分が上がるか?
•手入れが簡単か?
“未来の自分”より、“今の自分”に似合うものを残しましょう。
私の場合、今持っている服は23着。
季節によって変わりますが、フルリモート勤務なので、自分がリラックスできるものだけを厳選しています。
※服の断捨離方法、選ぶ基準をより詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。
8. 家具・収納具|モノが減ったからこそ、不要になる

服や雑貨を手放していくと、「あれ?この収納、もういらないかも」と気づくタイミングが来ます。
収納は、「モノが多い生活」を前提とした道具です。
思い切って、収納そのものを手放すことで、よりスッキリした暮らしに近づきます。
そして人間は、収納があると物を入れたくなる生き物。
「空白の原則」と呼ばれる習性で、
◯×5=25
の「◯」の答えをすぐ出したくなるのと同じ。
空白がなければ脳が気にすることもないので、空白を生み出す収納はどんどん減らしましょう。
9. 思い出のモノ|最後まで保留でOK

写真、手紙、プレゼント、卒業証書…。
思い出のモノに向き合うのは、断捨離の“最終章”です。
ここで焦ってしまうと、断捨離で後悔します。
だからこそ、最後に持ってくるのが正解。
どうしても手放せないなら、「思い出ボックス」にまとめて、“保留”にしておいて大丈夫です。
1年かけて気持ちを整理し、じっくり減らしていきましょう。
まとめ|順番を守れば、誰でもできる
断捨離の最大のコツは「正しい順番を守ること」。
捨てる技術は、筋トレと同じです。
簡単なところから始めて、少しずつ判断力と感情との向き合い方を鍛えていく。
その積み重ねが、やがて「本当に必要なモノだけの、快適な暮らし」へとつながっていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
少しでも参考になれば嬉しいです。
下部にある「このブログに投票」のバナーをクリックいただけると励みになります!
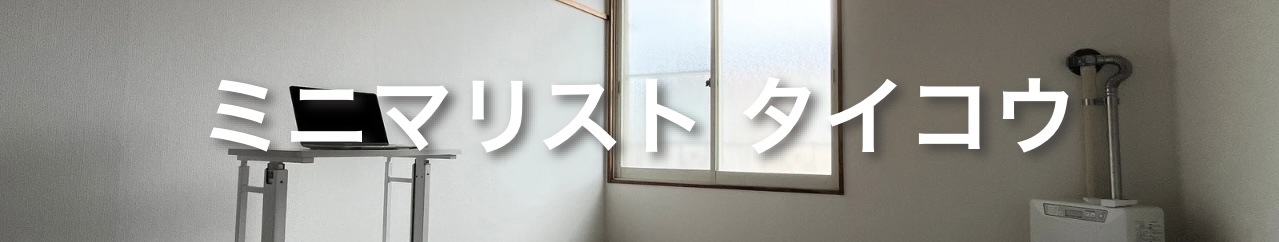
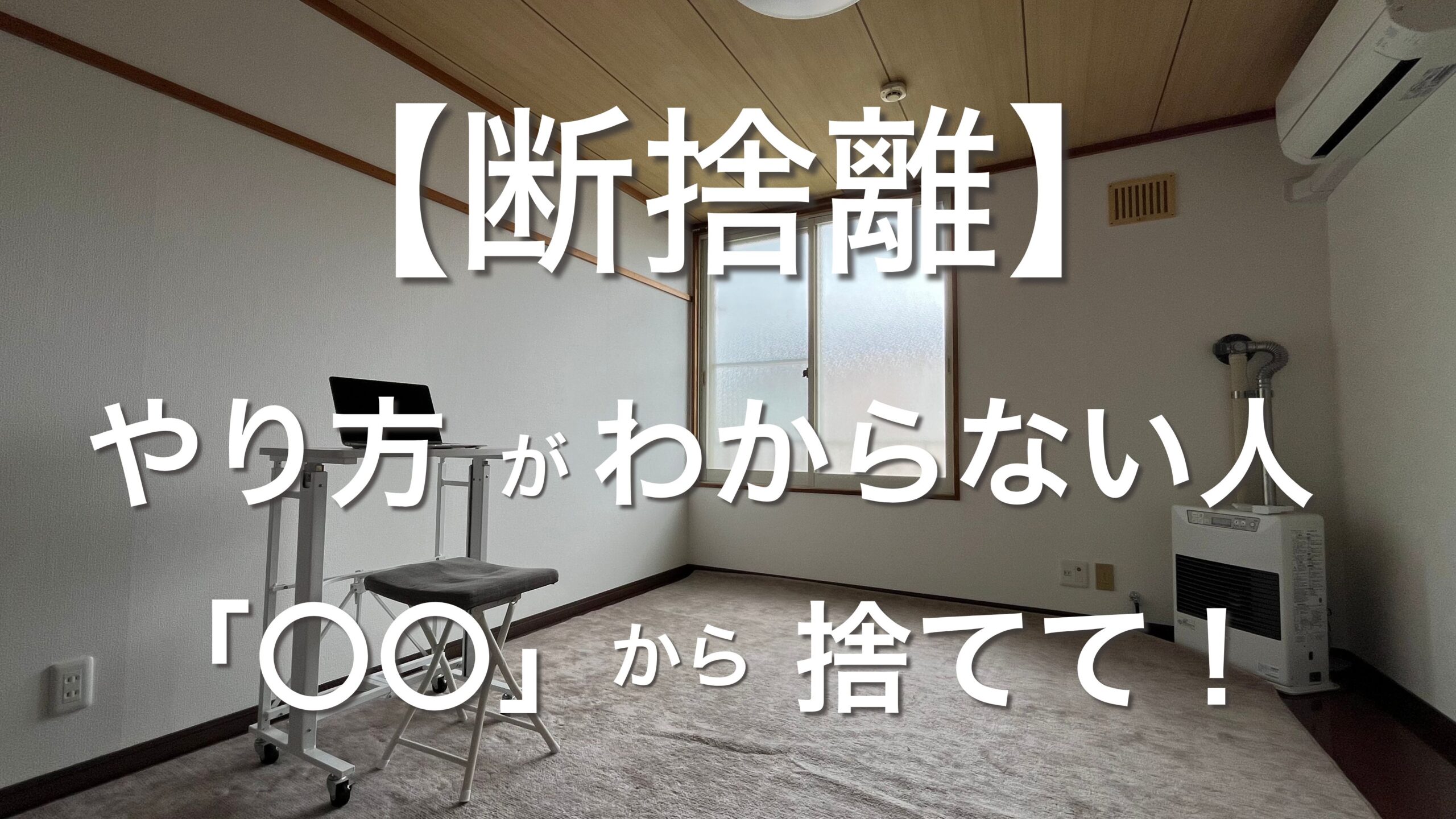

コメント